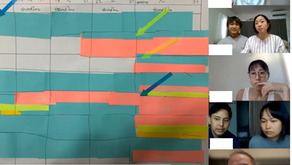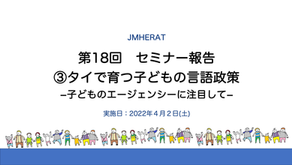タイにおける母語・継承語としての日本語教育研究会(JMHERAT)について

タイにおける母語・継承語としての日本語教育研究会
- Japanese Mother tongue and Heritage language Education and Research Association of Thailand (JMHERAT)
タイで複数の言語・文化環境で育つ子どもたちの幸せを、子どもを取り巻く全ての大人たちが、それぞれの立場から考えていくために、この会を設立しました。
私たちは、子どもにとって育成すべきことばの力を、母語・継承語の枠を越え、「自分を理解し、人を理解し、社会との関係を拓いていける力」と捉え、アイデンティディは「継承」ではなく、子どもが主体的に形成するものであると考えます。そして、子どもたちのことばと主体的アイデンティティ形成のために何をしたらいいのか、どう考えたらいいのかを学び合うために、セミナーや勉強会、ワークショップなどさまざまな活動を実施しています。
この研究会が目指すこと
タイで育つ日本に繋がる子ども達は、幼い時から様々な言語や文化を行き来しながら、複数の言語と文化で育っています。しかし、単一的な言語・文化観で育った(例えば、日本国内で日本語環境だけで育った)親も教師も、このような子どもの現実がなかなか実感としてわかりません。そこで私たちは、複数の言語と文化で育つ子ども達の現実を知ることから始め、タイで育つ日本に繋がる子ども達のことばとアイデンティティの問題を考えていきます。
そのためにまず、複言語・複文化ワークショップを開催し、単一的な言語・文化観から脱却し、子ども達の現実に添った「複言語・複文化能力観」で子どもを、そして自分を捉え直すことを目指します。そして、セミナーではその能力観に立ち、子どもの現実に添った言語・文化教育を考え、具体的に構想することを目指し、親や教師たちの実践を機関や立場を超えて共有し考察していきます。
※「複言語・複文化能力」欧州評議会言語政策局(2006)
「私たちの考える複言語・複文化能力観について」は、こちらから
歴史
2006年に、バンコクとチェンマイで働くインター校や大学の教師4人で、タイで育つ子どものことばの問題を考えるために設立。当時はタイに限らず、親も教師も、子どもの日本語教育を「国語」として捉えているのが一般的で、それが難しい子ども達には、「外国語としての日本語教育」と捉えることが主流だった。「国語」は日本という環境で生まれ日本語を自然習得した子ども達の読み書きを中心に行う教育で、「日本語教育」は母語を習得した大人を対象に発展してきた教育である。そのため、どちらも日本以外の国でことばを育む子どもには適していない。そこで、日本で育つ子どものための「国語」でもなく、大人を対象に発展してきた「日本語教育」でもない、タイで育つ「子どものための日本語教育」の在り方を考えるために設立したのがこの会である。研究会名にある「母語・継承語」は、日本国外で育つ子どものための日本語教育を考えるための観点として掲げた。
2009年から2010年は1年間活動を休止し、2011年に活動を再開。2011年から、「複言語・複文化ワークショップ」を実施。この年、「複言語・複文化」を可視化するためのツールとして「言語マップ」を開発。翌2012年には、子どもの言語発達を考えるセミナーを開催。以来、日本から招いた専門家も交えて、「複言語・複文化ワークショップ」と、子どもの成長とことばの育成を課題にしたセミナーの二つを開催することが活動の柱となった。2013年には、多様な子どもの現実を知るため、一年間対外的なイベント等を実施せず、すでに成人した子どもに対する聞き取り調査を中心に活動した。これをきっかけに、ことばだけでなく、子ども自身のアイデンティティについて考えることも、研究会の大きなテーマになった。2014年に開催したセミナーでは、複数の言語・文化環境で育つ子どものことばの成長を、他者との関係性を軸に整理するツール「関係性マップ」を開発した。2016年からセミナーは「実践共有セミナー」として定着し、現在は、毎年8月の「複言語・複文化ワークショップ」、毎年3月の「実践共有セミナー」を活動の柱としつつ、学生会や子ども会など、子どもを対象としたワークショップや、親を対象としたワークショップ、保護者セミナーなどを開催している。
沿革
2006年 設立
12月
第1回セミナー「母語・継承語としての日本語教育」
2007年
2月
3月
6月
8月
11月
第2回セミナー「子どものことばを育てるために今親ができること
北部タイ日本語教師会との共催でセミナー開催「多言語環境にある子どもたちのことばを考える」
第3回セミナー「どうやって子供の言語を選択しますか~国際結婚家庭からの実例報告」
MHB大会発表「タイの継承日本語教育現状報告-2007」
第4回セミナー「タイ・日本の国際結婚家庭で育った子供の体験談を聞く」
2008年
6月
第6回セミナー「学校教育の立場から多言語教育を考える」
2011年
8月
第1回複言語・複文化ワークショップ「多言語・多文化から複言語・複文化へ -タイで育つ子どもたちを、新たな豊かさへ繋げる視点」(言語マップ)
2012年
8月
12月
第2回複言語・複文化ワークショップ(私たちの違和感―ドラマ活動)
第7回セミナー「~子どもをどの言語で育てるの?~子どもが自信をもって生きていくための言葉の力とその発達」
2014年
10月
12月
第9回セミナー「ある国際結婚家庭の子どもたちの成長―Sさん家族の29年」
第10回セミナー「ある国際結婚家庭の子どもたちの成長―Sさん家族の29年―第2弾」
2015年
3月
第3回複言語・複文化ワークショップ「タイで育つ子どもたちを、新たな豊かさへ繋げる複言語・複文化の視点 」 (関係性マップ)
8月
第11回セミナー「子どもが自信をもって生きていくためのこ とばの力とその発達」
2016年
4月
9月
第1回大学生会
12回セミナー「私とことばと、生きるということ 〜ダブルの学生の声を聴く〜」
2017年
3月
第13回セミナー「子ども自信をもって生きるための言語活動実践ーレベル差をどう乗り越えるか」
9月
第4回複言語・複文化ワークショップ「わたしを描く―言語マップで何が見えるか―」(言語マップと言語ポートレート)
12月
第1回子ども会(言語マップと言語ポートレート)
2018年
3月
8月
第14回セミナー「子どもが自信を持って生きるための言語活動実践―体験とことば」
第5回複言語・複文化ワークショップ「マップを描き、マップで語るわたしたちの言語・文化体験 親と子どもと教師たち―」(言語マップと関係性マップ)
2019年
1月
2月
3月
8月
第2回大学生会
第3回大学生会
第15回セミナー「複数の言語と文化で育つ子どものリテラシーを考える」
第6回複言語・複文化ワークショップ「親と子どもの話を聞こうー複言語・複文化を生きる7人の語り」
2020年
8月
第7回複言語・複文化ワークショップ「親と子どもの話を聞こう―複言語・複文化を生きる語りー」(オンライン開催)
9月
第16回セミナー「複数の言語と文化で育つ子どものリテラシーを考えるⅡ」(オンライン開催)
2021年
3月
第17回セミナー「継承日本語教育を考える― バンコクにある親子でつくるテーマ型活動教室の実践から ー」(オンライン開催)
8月
第8回複言語・複文化ワークショップ「親子で言語ポートレートを描いてみよう!」(オンライン開催)
2022年
3月
第18回セミナー「親と子の言語政策 ファミリー・ランゲージ・ポリシー」(オンライン開催)
★ 沿革の詳細はこちら
運営委員
深澤伸子(代表)
長くタイの日本語教育に関わってきましたが、子どもの日本語教室に関わったのがきっかけでタイで育つ子どもの問題を考えたいと、この会を設立しました。子どもの課題は、子どもを育てる親と教師、そして社会の課題でもあります。複数の言語と文化を生きるとはどういうことか、自分にも重なるこの課題を、様々な立場、様々な地域の皆様と考えていきたいと思います。
▼ 2025年度運営委員(アイウエオ順)
久保亜樹
大学在学中に外国にルーツを持つ子どもの母語・日本語学習を支援するボランティアをしており、日本語教師として来タイしたのを機にタイで2年間��運営委員をしていました。現在はマレーシアで日本語教師をしながら、オンラインで研究会の活動に参加しています。私自身も複数の言語と文化がまざり合う環境で生活するなか、研究会活動を通して様々な立場にある人々の言語と文化について学んでいきたいと思っています。
小林絢香
初等中等教育の現場で日本語を教えています。来タイ後に日本語教師の道を志し、初めて担当したのがインター校の放課後日本語母語クラスです。多様な背景を持つ子どもたちとの教室での出会いが母語・継承語教育について考えるきっかけとなり、JMHERATのセミナーやワークショップに参加してきました。週末は娘とバイリンガルの子どものための日本語教室同好会に参加しています。
宍戸大作
2010年来タイ。金融機関から転職して日本語教師に。現在は大学の機関で日本語教育・文化交流事業に従事しています。フィリピン人の妻とタイで子供を持つことに悩んでいた時に本会に出会い�、貴重な学びとアドバイスを頂きました。複数の言語と文化、そして環境の変化に揉まれながら成長する娘を見て、直面する課題と当事者と共に学び続ける事の重要性を実感しています。
篠田百杏
2023年8月に初めて来タイし、現在タイの大学で日本語を教えています。外国にルーツを持つ子供のプレクラス日本語学習支援やタイでの日本語教育インターンの経験からタイでの日本語教育や継承語教育に興味を持つようになり、2022年から運営委員として携わらせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
千石昂
2018年にタイに住み始めた駆け出し日本語教師です。複言語・複文化環境で育つ子どもに直接触れ合ったり教えたりすることは普段全くないのですが、セミナーに参加する中で興味を持ち、関わらせていただくようになりました。複言語・複文化を生きる人たちの語りを聞いたり議論したりする過程で、人がものを学ぶとはどういうことなのか、��日々考えています。
田中伶弥
2024年6月来タイし、タイの大学で日本語を教えています。日本では3年ほど外国につながる子どもの日本語教育に関わっており、その流れでこの会の活動や継承語教育に興味を持ち、2024年10月から運営委員として参加させていただくことになりました。みなさんとのかかわりを通して、たくさんのことを学んでいけたらと思います。よろしくお願いいたします。
常見千絵
JMHERATは私にとって居心地のよい場所です。お誘いを受け、2018年から活動に参加しています。大学ではダブルの学生と接することが多く、彼らの人生に興味を持つようになりました。様々な人と出会い、学びも多くあります。これからも人との関わりを通して学んでいけたらと思います。
ツムサターン真希子
1998年にタイに渡り、現在はタイの中等教育機関で日本語を教えています。日・タイのダブルとして育つ我が子をきっかけに、複文化・複言語環境で育つ子どもたちの言語環境に関心を持つようになりました。セミナーやワークショップ、勉強会などを通し、継承語教育についての理解をより深めていきたいと考えています。現在は休会中です。
蜂須賀真希子
以前、タイの大学や中等教育機関で日本語を教えていました。日本に暮らす外国にルーツを持つ子どもたちへの日本語教育に携わったのをきっかけに、2023年から運営委員です。現在はベトナムからオンラインで参加しています。複数の言語と文化の中で育つ子どもたちのために、日本語教師は何ができるのかを学び、考えていきたいです。
松岡里奈
2019年までタイの大学に勤務していましたが、現在は関西の大学に勤務しているため、JMHERAT本体の活動ではオンラインを中心に運営委員活動をしています。また、私自身はタイ人の夫を持つ妻であり、今年6歳になる子どもの母親でもあります。親の悩みや想いに寄り添っていく場づくりを目指したいです。
松本みなみ
現在、タイの日本語教育機関で働いています。JMHERATの活動を通じて、複言語・複文化の環境で育つ子どもたちや保護者の方々など、さまざまな立場の方々と出会い、お話を伺う機会がありました。そのたびに、多くの学びがあります。今後も、複言語・複文化の中で育つ子どもたちのために、自分に何ができるのかを考え、学び続けていきたいと思います。
ミキ・ウティチュウォン
バンコクで親子セミナーに参加し、自分の人生を見直すことで世界が広がりました。まだ来タイ1年ほどですが、タイ語を勉強しながら自分の世界を広げている最中です!日本って、日本語って…バイリンガルって言葉だけ…?色々な角度から考えを深めていきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
村木佳子
タイの大学で働いています。タイのほか、日本、トルコ、アゼルバイジャンで日本語教育に携わってきました。日本では小学校でタイにつながりのある児童の学習サポートをしていたこともあります。日本語教師として、複数の言語/文化で育つ子どもたちのためにできること、言語教育のあり方について学びを深めていきたいと思っています。
渡邉あやめ
大学、大学院で日本語教育について学び、2019年から2020年、2022年から2025年の約4年間、タイの大学で日本語教育に携わりました。様々なルーツや家庭環境をもつ学生の言語環境に興味があり、2022年度から運営委員として活動させていただいています。
日本部会運営委員
松岡里奈(代表)
2011~2019年の間の約5年間タイの高校・大学で日本語教師として勤務しました。現在は関西の大学に勤務し、タイ人の夫と息子(幼稚園年長)の3人で暮らしています。我が家の家庭内言語は関西弁とタイ語。タイにつながりのある家族が、我が家も含めて、日本で生き生きと暮らしていく力となれますように。
ニラモン
ラウィナン
東京で継承語(繋生語)教育を研究しているタイ出身の留学生です。2021年から現在にかけて、大学院で学びながら、日本で育つタイにルーツを持つ小学生を対象に、継承タイ語の教育実践を行っています。また、大学や個人レッスンを通じて、日本人向けのタイ語講座も担当しています。JMHERATとの出会いは、複言語・複文化に関心を持ち、2022年にオンラインワークショップに参加したことがきっかけでした。タイの日本人コミュニティのように、日本でもタイ人が安心して暮らせるコミュニティをつくりたいという思いから、2023年よりJMHERAT日本部会に参加しています。
橋本洋二
1991年より日本語教育に従事。1993〜2020年、オーストラリアの三つの大学で日本語教育や留学指導にあたってきました。日本に繋がる海外在住の若者や子どもの言語とアイデンティティーの関係や繋生語/継承語教育に関心があり、近年は豪州繋生語研究会などで活動中の元・帰国子女。タイとのご縁は2022年のJMHERATワークショップから。現在、岡山県笠岡市に豪州人パートナーと二人暮らし。
藤井瑞葉
2015年から2023年まで8年間、駐在の帯同家族としてバンコクに住んでいました。現在は神奈川県小田原市に住んでおり、外国ルーツの児童生徒、定住者、留学生などへの日本語支援に携わっています。娘が0歳から8歳まで過ごし故郷のように感じているタイと、この活動を通して関わっていけることを嬉しく思っています。
嶋田俊之
2000年から2003年まで、ラチャパットチェンマイという大学で日本語を教えていました。チェンマイに行く前、バンコクで仕事を探している時に深澤先生と出会いました。日本に帰国後、小学校教員免許を取得して、2005年から2008年までマニラ日本人学校、2008年から2009年までシンガポール日本人学校、2009年から2016年までバンコク日本人学校、2016年から2020年までタイのシラチャ日本人学校で小学校教員として勤務していました。帰国後、千葉県の小学校で教員として働いています。私にもタイ人の妻がおり、中学生の長男、小学生の次男、長女の3人の子どもがいます。
タンパニチャヤーノン 遥
学生時代にタイの大学への留学を経験し、卒業後、再度渡タイし就職、出産、子育てを経験しました。2021年に京都の田舎に引っ越し、タイ人の夫、2人の娘、秋田犬1匹と暮らしています。夫の大学の恩師にJMHERATの「語り場」を紹介していただき、オンラインで参加したのをきっかけに今回メンバーに加わりました。
松本夏奈
大学時代にタイ語を専攻し、タイ語やタイ文化に深く親しんできました。在学中には、タイの中等一貫校で日本語を教える機会を得たことをきっかけに、タイにおける日本語教育に興味を持つようになりました。現在は都内の大学院に進学し、日本で暮らすタイの方々が生活の中で直面する日本語の困難をどのように解決できるのかを研究しています。みなさまの日本での生活が、少しでも安心できるものになるようお手伝いできれば幸いです。
村崎愛
2009年からタイの中高一貫校で1年、大学で10年、語学学校で4ヶ月、日本語教師として勤めました。タイ人の夫との間に2人の子どもがいます。現在は子どもと3人日本に戻り、夫とはタイ日の遠距離生活です。長崎の日本語学校に勤務しています。子ども達はタイで生まれたので、最初はタイ語しか話せませんでしたが、幼稚園に通うようになると1ヶ月で日本語オンリーになってしまいました。簡単な言葉はタイ語を使っていますが、タイ語での会話はできなくなってしまいました。これから挽回していきたいところです。
松崎舞子
タイ人の夫との間に9~18歳になる4人の子どもがいます。2007年からタイに住んだり日本に住んだりして子育てをしていましたが、2012~2016年はバンコクのインター校に勤務しながら子育てをしました。当時自分の子どもたちの言語発達や継承語教育に関心があり、その間に深澤先生に連絡してJMHERATの親子での活動を見学させていただいたり、セミナーに参加させていただいたりしました。現在は子どもたちと帰国し長崎県で日本語教師をしています。インター校時代は学校の方針で日本にルーツのある生徒たちに国語の教科書を使用した「国語」の指導をしており、子どもの言語発達に対する家庭環境の影響の大きさと、それを無視しての教科としての「国語」指導の限界を日々強く感じていました。
舟橋一揮(休会中)
2015~2022年までタイで働いていました。タイ人の妻と子供2人(7歳、3歳)と現在は千葉で暮らしています。普段は会社員として働いておりますが複言語での子育てについてヒントがあるのではと考えておりJMHERATの活動に参加しています。初めて日本で生活する家族と日々色々な発見をしながら楽しんでいますが、思うようにいかないこともあったりします。この活動で同じような境遇の方とも良いきっかけになるようにしていきたいです。